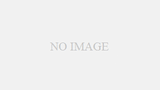【教師期待効果(ローゼンタール効果)で子どもを伸ばす!】
~「期待」が子どもの可能性を引き出す魔法~
「この子はきっと伸びる!」
そんな期待が、子どもの成長に大きな影響を与えることをご存じですか?
教育心理学の研究によると、大人が子どもにポジティブな期待を持ち、関わることで、子どもの成績や学習意欲が向上することがわかっています。
この現象は「教師期待効果(ローゼンタール効果)」と呼ばれています。
📖 小説『逆ソクラテス』に見る教師期待効果
最近読んだ伊坂幸太郎氏の短編小説『逆ソクラテス』の中に、教師期待効果を示唆する場面がありました。
物語では、ある担任教師が特定の生徒に対して「お前はダメなやつだ!」と決めつけ、否定的な言葉を繰り返します。
その結果、クラスの雰囲気が悪くなり、周囲の子どもたちからも「ダメなやつ」と見なし、本人も自信を失ってしまうという負の連鎖が生まれました。
しかし、その状況を見た仲間たちは、プロ野球選手に協力を依頼し、「ダメなやつ」と言われていた仲間にポジティブな経験を与える計画を立てました。
プロ野球選手は、ただ褒めるのではなく、的確なアドバイスを与え、「できる!」という成功体験を作り出しました。
その後、その子はプロ野球選手として活躍するまでに成長しました。そんな伏線のある内容でした。
🔬 教師期待効果(ローゼンタール効果)とは?
教師期待効果とは、「教師や周囲の大人が子どもに対して持つ期待が、その子どもの成績や行動に影響を与える」という心理学的現象です。
この効果は、1968年に心理学者ロバート・ローゼンタールと教育者レノア・ジャコブソンによって提唱されました。
📊 ローゼンタールとジャコブソンの実験
- 小学校で全生徒にIQテストを実施(実際には一般的な知能テスト)。
- ランダムに選んだ生徒を「今後、知能が向上する」と教師に伝える。
- 1年後、その子どもたちの学業成績が向上し、学習意欲や態度が変化していた。
この結果から、「教師の期待が子どもの成長を促す」ことが明らかになりました。
教える側が期待を掛けると自然と、それを前提としたかかわり方をするのは思い当たるところもあるなぁと感じました。
そして、人間の本能で「良くない」ところを見つけてしまう周波数のアンテナをたたみ、子どものいいところを見て褒める「アンテナ」に「意識して付け替えて」、子どもとの接し方の基本にしている当教室の方針に通じるところがあると思いました。
このローゼンタール効果を知ったとき、私は「当教室での取り組みは、まさにこれを実践している!」と感じました。
🌱 当教室での実践と教師期待効果
- 子どもの「いいところ」を積極的に見つけて、言葉にして伝える
- それができる機会をつくる。(レッスン最後の発表の場でのスタッフからのコメント)
- 「できた!」という経験を積み重ね、小さな成功体験を大切にする
- うまくできなかったとしても、頑張ったことをねぎらい、明るい未来を印象付け信じて見守る
この積み重ねが、子どもたちの自信や学習意欲を引き出す大きな力になっています。
✨ 期待が子どもを育てる
子どもたちは、私たち大人のまなざしを敏感に感じ取ります。
「あなたはできる」「もっと伸びるよ!」という期待をかけることは、
「先生は信じてくれている」「頑張ればできるかも!」という前向きな気持ちにつながります。
(期待の応えようと努めるのはピグマリオン効果といいます。)
その相乗効果で「期待の力」を大切にしながら、子どもたちの可能性を信じ、伸ばす取り組みを続けています。
ダメダメとできていなところが口から出そうになったら、ぐっと飲みこんで
お子さんの「いいところ」をたくさん見つけて、たくさん伝えてあげてください!😊✨