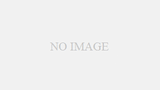【教師期待効果(ローゼンタール効果)の裏の面】
【教師期待効果(ローゼンタール効果)の裏の面】
前回は、子どもの明るい将来を見て期待すると、子どもが自信をもって伸びていくという「教師期待効果(ローゼンタール効果)」について書きました。
そして、それは当教室の「良いところを見つけて伸ばす」という考え方にもつながっていると感じるとも書きました。
🌱 「教師期待効果」の裏の面
しかし、これには裏の面もあります。
マイナスの面ばかりを見て、
- 「ダメなやつ」
- 「いつも同じことばかり間違っている」
- 「遅いのだから速くしなさい」
と、マイナスのことばかり言い続けると、
「悪い面」のローゼンタール効果が出てしまうことがあります。
だって、そうですよね。
小さいお子さんは、お母さんに褒めてもらいたくて、一生懸命なんです。
それなのに、何かあるたびにマイナスのことばかり言われてしまうと…。
たとえ「この子の将来のことを思って」と心の中でつぶやいても、その子にとって大切なのは「今の愛情」そして、未来への期待なのです。
🐀 「ローゼンタール効果」はラットでも実証された
「ローゼンタール効果」は、ネズミを使った実験でも効果が確認されました。
🐀 ネズミを使ったローゼンタールの実験(1963年)
大学生たちにランダムに選ばれたラットを渡し、「知能が高い」「知能が低い」と伝えました。
しかし、実際にはどのラットにも知能の差はありませんでした。
迷路学習の訓練を行った結果、「知能が高い」とされたラットは学習速度が速くなり、成績が向上しました。
これは、大学生の期待がラットへの接し方を変えたためと考えられます。
- ✅ **期待されたラット** → 丁寧に扱われ、トレーニングが熱心に行われた
- ✅ **低く評価されたラット** → 扱いが雑になり、訓練もおろそかになった
言葉でのコミュニケーションが取れないラットでさえ、「期待の違い」が行動に影響を与えたのです。
これは、人間にも当てはまることですよね。
不機嫌な人には優しく声をかけづらいですし、怖いと感じる人には近寄りたくなくなります。
子どもも、大人の態度や表情を敏感に感じ取っているのです。
🔍 どうしても「足りないところ」に目がいってしまう理由
でも、どうしても欠けた部分や足りないところに視点が向いてしまうのは、人間の本能ともいわれています。
なぜなら、私たち人間は、かつて「捕食される側の生き物」だったから。
周囲の変化にアンテナを張り、少しの違いも見逃さず、危険を察知して逃げる。
これは、太古の昔から人の本能に刷り込まれた危機管理能力なのです。
だからこそ、
逆に意識的に
- ✅ 良いところを見つけて褒めよう
- ✅ 認めよう
- ✅ 言葉にして伝えよう
としないと、悪いところばかりに目がいってしまうのです。
🌸 良いところを見つけて褒める習慣を
「良いところを見つけて褒める」のは、普段から習慣にしていく必要があります。
プログラマーの仕事には「デバッグ」という作業があります。
プログラムやコンピュータシステムのテストを行い、バグ(不具合)を見つけて修正する作業です。
バグを見つけるためには、あらゆる場面を想定し、失敗しそうなポイントを探し出します。仕事ではこちらが求められる能力なのは間違いありません。
だからこそ、家族の中でもそんな視点のまま子どもの行動を見ると、どうしても「バグ(ミス)を指摘したくなる」かもしれません。
そんな時こそ、意識して
- ✅ 「今日も元気でいてくれてありがとう」
- ✅ 「自分の元へ生まれてきてくれて嬉しい」
と、些細な幸せに目を向けてみてください。
これもまた、習慣にしていくことで、少しずつできるようになりますよ。😊