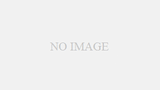100点じゃなくても、「もう一回!」が言える子に。
~認知能力と非認知能力のお話~
🐳 はじめに
こんにちは。すまいる・キッズのとどちゃんです🐳
最近よく聞く「認知能力」と「非認知能力」という言葉。
ちょっと難しそうな響きですが、実は、子どもたちが毎日使っている大切な力なんです。
今回は、その2つの力について、とどちゃんの言葉でやさしくお話ししてみたいと思います。
🧠 認知能力ってなあに?
たとえば…
- 計算ができる
- 文字が読める・書ける
- 覚えるのが早い
- テストでいい点が取れる
こういった「目に見えやすい力」のことを、認知能力といいます。
🌱 非認知能力ってなあに?
それに対して…
- 最後までやり抜く
- 間違えても立ち直る
- 自分に自信がある
- お友だちとうまく関われる
- 「なんで?」「やってみたい!」という好奇心
こうした「心の力」「生きる力」が、非認知能力です。
💡 どっちが大事? って、そういうことじゃないんだ
最近は「非認知能力が大事!」と言われることが多くなってきました。
でも、だからといって「勉強なんて意味ないよ~」ってことではありません。
もちろん、すまいる・キッズでは認知能力を育てる学びも大切にしています。
大事なのは、“どちらか”ではなく“どちらも”。
そして、それがどうつながっているかなんです。
🌸 子どもたちを見ていて思うのは…
どんなに勉強ができても、 「どうせ自分なんて…」と思っていたら、チャレンジできません。
チャレンジしなければ、経験がたまらない。 「やってみてうまくいった!」という成功体験も、 「うまくいかなかった。どこが足りなかったかな?」という学びの時間も、 チャレンジなしには生まれません。
でもね、たとえ今はうまくいかなくても、 「失敗しても、またやってみよう!」と思える子は、 あとからちゃんといろんな力が身についていくんです。
どんな自分でも大丈夫、という心の土台
そんな気持ちが心の中にある子は、すごく強い。
🧩 すまいる・キッズで育てたいのは、そんな“心の根っこ”
- 「できた!」という経験
- 「やってみよう!」という気持ち
- 「失敗しても失敗しても安心できる」空気
すまいる・キッズでは、 プログラミングやパソコンの学びを通して、 子どもたちの「認知」と「非認知」の両方の力を、 バランスよく育てていきたいと思っています。
勉強(認知能力)だけでもダメ。
自信や粘り(非認知能力)だけでも足りない。
これからの社会では、 「知っている」だけじゃなく、「活かせる」「つながれる」ことが大切なんだと思います。
つまり、
「学ぶ力」と「人として生きる力」は、セットで初めて価値になる。
子どもたちが、 「自分らしく、誰かと一緒に、生きていける力」を これからも、すまいる・キッズでじっくり育てていきたいです。
🐳 さいごに
「認知能力」と「非認知能力」。
最近よく聞く言葉だったので、自分でも調べてみて、 学んだことをブログにまとめてみました。
調べる=インプット
発信する=アウトプット
アウトプットすることで、記憶や理解が深まっていくのを感じています。
まだまだ学びの途中なので、もしかすると足りない表現や勘違いもあるかもしれません。 でも、こうして教室のブログにまとめることで、 今、子どもたちとどう関わっているか、どう育てていきたいかを、 あらためて見つめ直す時間にもなりました。
最後まで読んでくださって、ありがとうございました。
では、また🐳
(補足) 主な非認知能力の分類(OECDの枠組み)
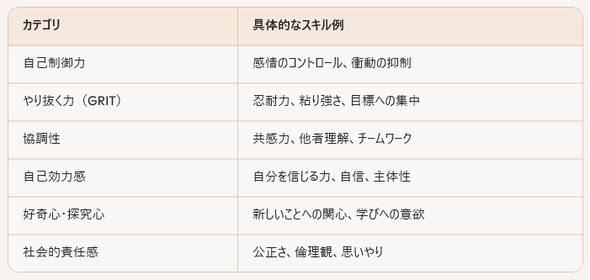
れらは数値化しにくいけれど、人生の成功や幸福に深く関わる力とされ、OECDは「認知能力と非認知能力のバランスが重要」と明言しています。